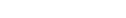
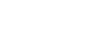
茶室だより
『令和七年遠州忌法要茶会』が『日本女性新聞』に掲載
「きれいさび」の武家茶道の美学
流祖から脈々と継がれてきた歴史と未来への希望を繋ぐ茶会
 献茶式の様子
献茶式の様子
新緑が眩しい茶会日和の6月1日、東京都文京区音羽の護国寺茶寮で、茶道小堀遠州流の遠州忌法要茶会(主催=小堀遠州流家元小堀宗峯、後援=小堀遠州流松籟会)が開催された。
今年は小堀宗峯氏の家元継承を記念しての遠州忌法要茶会となった。午前9時より忠霊堂において献茶式が行われ、家元による献炭、献茶、読経、献香と続き、観世流能楽師・清水義也氏による祝いの謡、「養老」の後、茶寮において五席の懸釜が行われた。
 謡の奉納
謡の奉納
家元席の楓の間の床には、新家元の決意を示す沢庵一行の「諸悪莫作衆善奉行」が掛けられ、古銅柑口にいけられた稀少な花、敦盛草の美しさが際立つ。
そして小堀家伝来の名物茶入の「不聞(きかざる)」が記念すべき遠州忌法要茶会の席を祝した。この茶入は遠州が命名し門下に授けたものが再び小堀家に戻り三百数十年も伝承されてきたもの。関東大震災で箱などは消失したが、奇跡的に被害を免れたのは「茶入に具わった徳」とも言うべきと、小堀宗通の『小堀遠州の茶道』に記されている茶入である。
 家元席花 敦盛草
家元席花 敦盛草
幕末に生きた宗中結のこの上なく美しい羽箒の「青鸞」は、激動の時代でもしなやかに生き抜いていく美学を見せてくれる。小堀遠州流ならではの見事な「きれいさび」の道具組の濃茶席だった。
青年部の立礼席の寄付の床は「雨中柳燕図」で、本席の床には雨を詠んだ十二代宗舟筆の扇面和歌。雨に打たれても凛とした姿を描く紫陽花「黒姫」と白糸草と藺の花籠に込められた新家元への想い。
 青年部席点前
青年部席点前
献茶席では遠州本形牙、家元席は四代宗舟作銘「さかひ」に、月窓軒は十六代宗圓作銘「郭公」、艸雷庵は当代宗峯作「東雲」と代を重ねて繋いできた歩みの茶杓が揃う。
「小の字透かし」や瓢箪など遠州好みの見事な「きれいさび」の室礼とお道具組に新しい趣向も取り入れた武家茶道の美学に浸る一日。流祖から引き継がれた歴史と新家元宗峯氏のもとでこれから始まる未来を感じる今年の遠州忌法要茶会だった。十一月に予定されている家元継承披露祝賀会が、今から楽しみである。
 楓の間
楓の間
(文:エッセイスト 橘さつき)
日本女性新聞 令和7年6月15日発行号より
撮影:熊谷秀寿


