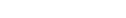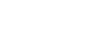流祖 小堀遠州
小堀 遠州(1579–1647)

小堀遠州公(政一)は江戸初期の頃、徳川幕府の重臣として文化に政治に行政にと活躍しました。 作事奉行として幕府や宮廷にかかわる建築、茶室や庭園の作事に関わり、その芸術的な美しさは今日まで高い評価をうけております。 遠州公は茶の湯を古田織部に師事し、徳川三代将軍の茶道指南として武家茶を確立、感性豊かに王朝文化への造詣も深く、藤原定家に起する定家様書体や、八分とも呼ばれる隷書体は遠州独特の世界をつくっています。
遠州の茶とは
遠州の評価について
千利休によって大成された茶道が、その孫宗旦によって「侘」一辺倒になった時、必然的に起こったのが遠州のいわゆる「芸術茶」でした。織部を経て利休の茶を継承し、その芸術的向上を図った遠州の茶道は、さまざまな点において宗旦流の「侘茶」とは対照的な位置をなしています。宗旦が利休好みの丸卓をさらに素朴に改めた同じ時代に、遠州は己の家紋たる「花輪違い」(七宝とも)小堀の「小」を主題とした「小の字透かし」、あるいは彼が最も好んだ「瓢箪模様」などを自由に駆使して、さまざまな棚物、茶器を創作しました。ユダヤ人であるが故に、かのアインシュタイン博士と共にナチス・ドイツを追われ日本に亡命していた建築家ブルーノ・タウト氏(1880~1938年)は、遠州を評して「日本の生んだ最大の芸術家」と称していますが、彼が茶道に、建築に、庭園に、美術工芸に寄与した史的功績は決して看過できぬものがあります。
小堀遠州は藤原秀郷の後裔と称せられ、幼名作助後政一といい、孤篷庵大有宗甫と号しました。遠州という通称は、彼が慶長十三年遠江守に任ぜられてからのことです。
新井白石は『藩翰譜』第六において遠州を称して、
「その道のことはいふに及ばず、手能くかき、歌よみ、眼高く、書画万の器翫悉く其鑑定を待ちて、世の価を高下す。されば水よりいでし氷、藍より出づる青色、世々の先達を超過して、上中下のもてなし譬をとるに言葉なし云々」
と述べているように、遠州は茶道ばかりでなく、さまざまな方面においても卓越した才能を有していました。
師匠古田織部とのつながり
彼がいつ頃から古田織部に茶道を師事したかは不明ですが、晩年松屋久重に語って言うに、「十歳の頃利久に会ひたるよ……大和大納言殿へ太閤殿下御成りの時給仕を仕りたる云々」(『松屋会記』)とあるように、十歳の折早くも千利休に会い、その前年の天正十五年には当時天下の視聴を集めた北野大茶会が行われ、子供心にも茶道に対する関心は非常に深められたことと思われます。また文禄三年二月三日、十六歳の折には、父正次に伴われて松屋久政の茶会に臨んだ記録も残っているので、おそらくは十歳ごろより北野大茶会に刺激されて古田織部の門に入ったのではないでしょうか。
遠州と王朝文学
遠州の茶道の性格を知るためには、まず彼の文学を理解しなければなりません。遠州は藤原定家の末たる冷泉為頼に和歌及び書道を学び、優美な王朝文学を深く愛し、東福門院(後水尾天皇中宮、徳川秀忠の女和子)の選ばれた「集外三十六歌仙」の一人に選出されたほどでした。当時和歌の神とまで称せられた定家卿に深く私淑していたようです。
道歌として、「茶の道は思ふに深きむさしのの 月の出しほをさして行くかな」「秋の夜のねざめにせめて思へかし 日々にみたびはかへりみずとも」などがあります。
こんな話も伝えられています。加賀大納言がある時定家の軸を求め、それを床に掲げて遠州を招いたことがありました。遠州はその軸を一瞥したのみで一向に賛美する気配もなかったので、一座はなんとなくしらけてきました。そこで茶坊主が遠州に耳打ちして「実はあの軸をご覧に入れるため、わざわざあなたをお招きしたのです」と言いました。すると遠州は笑って、「あの掛物正しくわが筆にて候。わが手跡をいかでほめ申すべきや」と言われて茶坊主はその返事に窮し、ただただ遠州の能筆に驚嘆したといいます。
遠州の文学に対する素養は、彼の茶道の上にも反映しています。「きれいさび」と称せされている華やかな内に一抹の寂しさを宿す彼の茶道は、優美なそして繊弱な王朝文学に一脈相通ずるものがあり、彼が好んで茶入、茶杓の銘に王朝文学の和歌を採用したのは、その一つの現れでもあります。茶器の「歌銘」は遠州を持って嚆矢とするものではありませんが、彼がもっぱらこれによったため、後世の茶人達が、それに倣うようになりました。