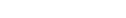
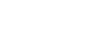
茶室だより
神奈川支部研修会「飯後の茶事」に寄せて 2024年10月26日(土) 鎌倉芸術館[神奈川県鎌倉市]
鎌倉芸術館に於いて「飯後の茶事」の研修会が行われました。
「飯後の茶事」というのはお客様が食事をすませてから行われる茶事のことで、「お菓子の茶事」とも言われます。
まず、寄付で正客、連客、お詰の役割等の説明の後に、香煎を頂き亭主のお迎えで本席に向かいます。
初座の床、道具の拝見の仕方、正客と亭主の会話のやり取りについての説明後に一人ずつ実践しました。
亭主の床の間の室礼は、初座は掛軸と香合、後座は花と香合となりますが、最初から掛軸と花、両方飾る「諸飾り」もあるそうです。
拝見が終わると炭点前になり、その後主菓子をいただき、中立となります。
銅鑼等の鳴り物を静かに聞き、頃合いを見て本席に移ります。
後座が始まります。
後座の室礼の拝見が終わるとメインであります濃茶点前が始まります。
亭主と正客で床、菓子、茶名、詰元、道具の事などのやり取りしながら席を進め
「引き続きお薄を差し上げます」の声に干菓子が出されます。薄茶点前が開始、何人かのお茶を点てた後、正客がお詰に手替わりを所望し、亭主に茶を喫するよう正客が指示し、全員茶を喫したら亭主は手前に戻り席を進め、最後に道具を下げ、箱書き、書き付けなど補足説明等をした後、挨拶を交わし客は名残の拝見をした後退出する。
これが飯後の茶事の流れですが、この流れを把握していますとすべての茶事に共通しているため、諸々の茶事に対応できるとの事です。
あとは懐石のいただき方を勉強すれば困らずにお茶事を楽しむことができますので、次回は「懐石のいただき方」の勉強をして頂けると嬉しいのですが・・・
研修会担当の先生方のご尽力で茶道に関連した講習会を開いてくださるので、茶道が「総合芸術」であることを再認識させられる今日この頃でございます。


神奈川支部 増田宗斐


